| 流派と殺法 |
|
|
当然の事ですが実践のみにベクトルを向けられた技術である事は周知の事実です。
流派は近藤勇はじめその門下が使う天然理心流、神道無念流、無外流、北辰一刀流、宝蔵院流などなどホントにいろいろです。
中でも神道無念流は実践向けの剣術の達人が多く、この流派の達人とさしで立ち向かったら、かなりの確立で神道無念流が勝つのではないかと思う程です。天然理心流の達人たちもこの流派の達人を手に掛けようとする時は、確実に仕留める目的もありますが、決して真っ向勝負を仕掛けていません。
北辰一刀流は当時とてもメジャーな剣技で、“竹刀” を持たせたらやたら強いと評判でした。尊攘派の強い思想を持った士族に人気があった流派だった為、文武両道と呼ばれる人達が多くいました。しかし、思想が強過ぎる堅物が多かった側面もあるようです。特に天然理心流の近藤らは北辰一刀流を主線とする者達と主義主張やソリが合わない、意志疎通がすれ違う場面が多々あります。そしてこの流派の剣術家は少なからずも紳士的であり、理詰めで迫ろうとするがゆえ、実践に於いては当時の他流派の達人のように実践感覚の冴えた勘と無慈悲な冷酷さを持てず、逆に切られる事が少なくありませんでした。
近藤勇は稽古の時、
「気組だ! 気組だ! 剣は気組だ!!」(気合)と声を荒げていたと言いますが、実践における強さの秘訣は技術はもちろん、心の持ち方ひとつでどんな達人でも負けもするという事なのでしょう。 |
|
|
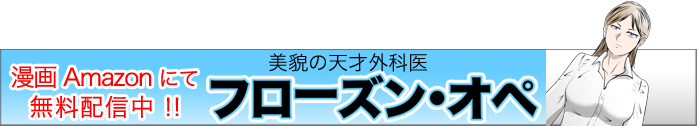
|
|
|
|
|
| 稽 古 |
|
|
当時の天然理心流の稽古は、極太の重い丸太の様な木刀を素振りするのが、基本の練習方法だと言います。
腕力に大きく依存した練習方法だったようです。
無骨な近藤勇しかり、美男子で描かれる沖田総司ですが彼などは肩幅が大きく張った長身の男だったといいます。しかし、土方歳三は意外とやさ男ですね。写真を見る限り筋肉隆々の体だったようにも見えません。技とスピード・知恵で戦うタイプだったのかもしれません。細い体の武術の達人も多いのも事実です。
近藤勇は天然理心流の道統を継いだだけあって、その教え方は一級品だったと言います。
さらに、彼の人徳もあり他流派から多くの人が彼の門下生に加わっています。
それに比べ、天才と謳われている沖田総司の稽古の付け方は、とても荒っぽく無茶苦茶な練習を弟子に強いていたと言います。恐らく天才肌の彼は難しい技や練習でも何の問題もなく卒なく出来る為、彼からすると出来ない事の方が理解できなかったのでしょう。
それに比べ、天才と謳われている沖田総司の稽古の付け方は、とても荒っぽく無茶苦茶な練習を弟子に強いていたと言います。
恐らく天才肌の彼は難しい技や練習でも何の問題もなく卒なく出来る為、彼からすると出来ない事の方が理解できなかったのでしょう。 |
|
| 沖田: |
「もーっ !! 君達なんでこんな簡単な事が出来ないのぉ ?!
こうするだけだよ。 ほれっ!」 |
| 弟子: |
「……。そ、それって…、沖田さんだから出来るんですよぉ。
そんな出来ませんよ、普通…。 三つの突きが一本に見える技なんて…。」 |
| 沖田: |
「なーんでっ?!」 |
こんな感じだったのかも知れません。
|
|
| 得 意 技 |
|
|
新撰組のよく使った得意技としてよく知られるのが、"突き"です。
彼らは切るよりも突いたとよく言われています。
| 最も有名なのが、新撰組三番隊のリーダー・斉藤一の「左片手一本突き」と沖田総司の「三段突き」です。(彼らの剣技の詳細は「新撰組の編成と3強」で述べます。) |
剣術の技術の中でも"突き"はとても高度な技のひとつです。この突きという技は、一見とても素朴で簡単な技なように聞こえますが、突きはなかなか相手をとらえる事が出来ず、全身を大きく使って繰り出す技の為、決まれば確実に致命傷を負わせる事が出来ますがしくじった時の隙が大きくカウンターを喰らいやすいのが、大きな特徴でありデメリットとなります。
真剣の勝負においてこの突きを繰り出すと言うのは、技量がどうのこうの言う前にカウンターを貰うリスクを背負っても討ち取るという、よっぽどの覚悟(死に対する)がないと思い切り突き貫く事は出来ません。
この技を得意としたという事は、死を恐れぬ絶対的な覚悟があったということでしょう。
とは言っても、腰の引けたヘタな突きや軟い戦いをして逃げ帰ったりすれば、いずれにせよ「士道不覚悟」で切腹の可能性が待ち受けていますから、生きる望みを決死の突きに賭けるしかなかったのでしょうけど。
|
|
|
| 暗殺と戦法 |
|
|
新撰組の暗殺の仕方・戦い方は、完璧な兵法の下に成り立っていました。
まず事前に敵方の全ての情報を徹底的に調べ上げ、完璧な情報収集を行います。
酔った時の立ち振る舞い、普段好んで通る道、剣技の太刀筋・構え方・パターンなど行動・素性・クセ・性格・好み、その他ありとあらゆる物を調べ上げます。敵の技量や心理を計った上でどう詰めるかを練っています。
戦いの場においては、正面からは達人を差し向け、後ろ・横全ての逃げ道には数人を張り込ませ、敵が逃げようものなら討ち取るという様な一切の逃げ道を塞ぐ絶対の勝利を勝ち取る戦法でした。
(新撰組に中途より加わり、主義主張で隊内を掻き回して事実上脱退した御陵衛士リーダー・剣豪の伊東甲子太郎を始末する時、またその仲間うちを討ち取る際には、御陵衛士メンバーに半端ない剣術の達人・服部武雄という人物もいたので上記の様な戦術、心理戦などを巧みに利用して討ち取りに行っています。)
|
新撰組が強い強いと言われるのは確実に敵を仕留めるからこそで、勝敗の分からない、いちかばちかの勝負は避け、勝ちを強く見込んだ勝負を仕掛けていたからだと言えるでしょう。
これは土方歳三の完璧な指揮の下に成り立った策略・戦法で、彼の軍師としての才が伺えます。
そして、こと暗殺にかけては三番隊のリーダー・斉藤一が重宝され、ターゲットを確実に仕留めて素知らぬ顔で帰って来る暗殺の天才でした。 |
|
|
**********************************************
見解に関する参考史実は、限りなく現存する記録に忠実に従うように努めています。
しかし、当時の証言や言動などに関しては、誰にでも理解でき楽しめるように、わざと難しい説明や固い言い回し、昔の言葉使いや表現などをせずに現代口語に変えて記載してあります。
|
■ 次ページ ■
 |
|

