| �e �p |
|
|
�������Ă���ʐ^�ɂ���ʂ肩�Ȃ�̒j�O�ł��B
�ߋ�����̋L�^�����Ă��A�j�O���ƌ����،������X�c����Ă��܂��B |
���u�g��ڌܐ��A���ڐ��G�j�V�e�������j�q�^���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�g���͖�168�p�A�u�₩�łƂĂ����j�q�ł���j
�@�@
���u���Ƃɓy���̔@���́A���҂Ƃł������������炢�̐F�j���镗�e�ł������̂��L������v
�@�@
���u���̂悤�Ȕ������U�藐���āA�����Ƃ����Έ�̔��j�q�Ɛ\���ׂ����e�Ɋo���܂����v |
|
�ȂǁA���ɂ������̏،�������ނ̗e�p����Ă��܂��B |
|
|
|
�ߓ��E(��165cm)���c���i(��170cm)�₻�̑���v�V��g���m�ȂǁA�F����ӊO�ƍ��̓��{�l�̐g���Ƃ����܂ő卷�Ȃ����炢�ŁA�����Ƃ��Ă͂����ԑ啿�ł��B�i�������̒j�q���ϐg��155�`158cm�j
�i�ē���/��175cm�E���c�@/��182cm�Ȃnj��\����Ȋ����j
�痧�����A�y���ΎO�͂��ߓ����̐l�̎ʐ^����ƃw�A�X�^�C����ߑ��A�ʐ^�̐F��������������������邾���ŁA�e�p�Ɋւ��Ă͌���l�Ƃ���قǍ��ق���������̂ł�����܂���B
�悭�l�����150�N�O�������A�l�͂���Ȃɕς���ĂȂ���Ȃ��̂��ȁH���Ďv����Ƃ���ł�����܂��B |
|
|
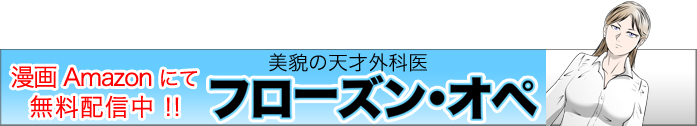 |
| �� �i |
|
|
��{�I�ɂ��ƂȂ������������Ă��āA���Â��Ȑl���ƌ����̂������̏،��̋��ʎ����ł��B
�@�@
�b������ΒP�������ɕK�v������[�I�ɘb���ׁA����������c�����₷�������Ɠ����̋L�^�ɂ���܂��B
�������A�{��Ƃ��ꂪ�肪�t�����Ȃ����ɍr���ׁA���{���ł͒��ɐ����I�Șb������̂����������Ƃ���܂��B
�@�@
���̎�̃^�C�v�̐l�͉��₩�Ȋ�����Ȃ�����A���[���Ɛl�̍s���ƌ������Ď@���Ă���̂��킾�����肵�܂��B�b������������Â��ʼn����C�ɂ��ĂȂ����̂悤�ɑu�₩�Ɏ��������܂����A���ۂ͑���̕��̒������������Ă���^�C�v�ł��B
�����A���c���i���ΌL���Y�A��㌹�O�Y�Ȃǂ́A�u�c�s�v���Ƃ��u�|���v�Ȃǂƌ���ꂽ�G�s�\�[�h��،����c���Ă��܂����A�y���ΎO�Ɋւ��ẮA�����A�ӊO�Ƃ��̗l�Ȍ������͂��Ă��܂���B
�A���A�r�c�����ςɌq����Í��r���Y��f������ׂɍs��������́A���u�̉i�q�V���������قǂ̏�e�͂Ȃ���i������Ă��܂��B
�Ƃɂ����y���ΎO�ɂ��ẮA�L���L���œ��̉�]�ƍєz���s�J�C�`���Ƃ����،��͑����c���Ă��܂��B |
|
| �،��ɂ́A�u�ڂ��͐l���˂�悤�Ȋ��������Ă����B�v�Ƃ��c����Ă��܂��B |
�\�����͒m���U�肵�ė]�v�Ȏ��͌��ɂ����A�b�����킹�ĂA����̍l����e�����ʂ��������ʼn����u����Ƃ�����m�̍s���p�^�[�������X�����܂��B
��O�҂ɉf��V��g�̕����E�y���ΎO�Ƃ́A���g�̈�̊���������E���A������������Ȃ���_�o���点�Ă��邻��ȃI�[�����������̂ł��傤�B
���̐����l�̐S����ǂޓ��@�̗͂D��Ă����l�������̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B
�����炱���A��p�Ɋւ��Ă͓V�˓I�ȍ˔\�������Ƃ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�]�k�ł����A���Ȃ݂ɋ��s�ȑO�̓y���ΎO�̑��҂���̐l���]�́A�u�ƂĂ��C���������z�̂����j�ŁA���l���ۂ������݂��Ă��邵�������Ȋ����������B�v�Ƃ��]����Ă��܂��B
���s����Ƃ͑S�R�Ⴄ��ۂł��ˁB
���Ԃ�A�f�̓y���ΎO�͂������Ȃ�ł��傤���ǁB |
|
|
| �� �p |
|
|
�ނ̌��p�́A�ߓ��E����c���i�ȂǂƓ����V�R���S���ł��B
�������A���̗��h�̖Ƌ��F�`�i�ŏ�i�ʁj�܂ł͍s���Ă���܂���B
�V�R���S���ɓ���O�܂łɂ������������̗��h���m�Â��Ă����ׁA�ςȃN�Z�������Ȃ��������炾�Ƃ������Ă��܂��B
�������A���H�ɂ����Ă��̌��͍Ⴆ�킽��A�ނ� �l���o���Z���p�͎��H�ŏd��V��g�����ӂƂ����Z���p�̊j�ݏo���Ă��܂��B
��͂�m�ÂƎ��H�ł͑S�������Ă��Ⴄ�킯�ł�����A���H�ł̐S�����悭�m���Ă������p�g�����Ƃ��������o����Ǝv���܂��B
����ɉ����āA�V��g�ɂ͘r�̗����҂��S���S�����Ă����̂Ō��̘r�Ƃ����_�����Ō����Ɖ���ł��܂��Ƃ����̂����邩������܂���B |
 |
�悭�V��g�̑��m�Ɍm�Â����Ắu�܂��܂����I�v�ƌ����ĔM�����Ă����悤�ł��B
�m�Â��y����ł���ނ̎p���ڂɕ����т܂��B |
|
|
|
| �G�s�\�[�h �@ |
|
�ߓ��E���V���{�R�ɕ߂܂������A�y���ΎO�͓G���ƌq����𖧂ɂ��Ă��������̖��b����C�M�ɂȂ�Ƃ��ߓ��̖��������Ă���Ă���ƒQ��ɍs���܂��B
���C�M�͂��̒Q�������܂����A���̖��ʂ�����鎖�͂���܂���ł����B���͊��R�Ƃ̌��Ŏז��ɂȂ肻���ȘA�����]�˂���ǂ��o���A�����J�饌��𗬂����ɍ]�˂�������j�Ƃ��ėL���ɂȂ����������ł����A�����𐾂��Ė������Ő�����g��Ɍ��̂Ă�ꂽ�V��g�ɂ͕s���Ɏv����G�s�\�[�h�ł�����܂��B
|
|
| �G�s�\�[�h �A |
|
���ق֖k��̍ہA���˂ɗ���������y���ΎO�́A�ނ̊�ʂƍєz���ĉ��H���ˁi���k�S��j�ő���R�̎w�������Ȃ����Əd�b�A�������Ă��܂��B
���̎��ɔނ͂��������܂��B
�u���̑�C���邩��ɂ́A������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ���������܂��B��R���w������ɓ������ẮA�R�߂����������Ȃ���܂Ƃ߂��܂���B�������A���̌R�߂�j��҂������Ȃ���̂�����ł���̂ĂȂ���Ȃ�Ȃ����ɂȂ�܂����A����ł���낵���ł����H
����ɂ��ّ�����������v���܂��B�v |
�y���ΎO�̃J�}�����������ł��f���܂��B
�A���̍����Ɩ{�C�x���Ď@���Ă����̂ł��傤�B
���̌��t�����d�b�A���́A����̓_�����ƌ����Ă��̘b���͖����������ɂȂ�܂��B
�����̐��˂̉ƘV�Ȃǂ́A���̌�u�y���Ȃǂ̓J�X���B����Ȃ̂Ƙb���Ȃǂ���ɒl���Ȃ��B�v�Ƃ����l�Ȏ̂đ䎌���c���Ă��܂��B
�y���͂��łɌ������Ă����̂ł��傤�B���܂ł������ł������悤�ɁA���������A���͂����Ƃ������ɐӔC�������t���Ď�̂Ђ��Ԃ��ē����čs�������B
����ȘA���ȂǁA�����̎��H�ł͑��X�ז��Ȃ����Ń��N�ȏ����ɂ��A�N�\�̖��ɂ������Ȃ����ɖO���O�����Ă����̂ł��傤�B
���炭�A�`�����̐ӔC�҂��Տグ�āA�����̍ۂ͑S�ӔC���������Ĕ˂Ƃ��Ė������ׂ̗��R�ɂ����������̂��z���g�̂Ƃ��낾�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���ہA���̂��Ɛ��˂̏d���͔��ɞB���ȑԓx�ōR�킵�Ă����܂��B
���H�����̐킪�u��������ɂ����Ă��A�����{�G���A�ł͋����{�̎����\�����܂����������������ꂩ��A�ُ̍�͐��˂����H�z��˓����̒��j��S���`�ŕ�C�푈�ւȂ��ꍞ��ł͍s���܂��B���A�������c�A��Âƈ���Đ��˂͖{������ꂽ�O��R�킷��܂łɂ͎��炸�A����f���Ȃ���̞B���ȓ����◧���ʒu��d��Ȃ���̒��r���[�Ȑ헪�̖��ɁA�債���R�������鎖���Ȃ��A�Ȑ틵�����ĂƂ�₠�����蔒����g���܂��B
|
|
| �� �� |
|
�y���ΎO���k�サ���قɒ��������ɂ́A�ނ͂������̊o������߂Ă����ƌ����Ă��܂��B
���̗��t���Ƃ��āA
| �u��������̐��ɐ������炦�鎖�����낤���̂Ȃ�A���̐��ŋߓ��B�ɍ��킹��炪�Ȃ��B�v |
�Ƃ������t�𑁂��i�K�Ŏc���Ă��܂��B
���قɓ����Ă���͐H�����e���ȕ����D��ŐH�ׁA�ґ���������A�ƂĂ����a�ŊF������ꂽ�ƌ����Ă��܂��B
���s�ŋ����ꂽ�⍓�ȋS�����́A�̂̎����ɖ߂��Ă��܂����B
|
|
|
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����Ɋւ���Q�l�j���́A����Ȃ���������L�^�ɒ����ɏ]���悤�ɓw�߂Ă��܂��B
�������A�����̏،��⌾���ȂǂɊւ��ẮA�N�ɂł������ł��y���߂�悤�ɁA�킴�Ɠ��������ł������A�̂̌��t�g����\���Ȃǂ������Ɍ������ɕς��ċL�ڂ��Ă���܂��B
|
�� ���y�[�W ��
 |
|
|
|

|

